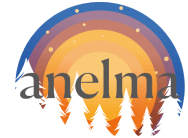目次
はじめに
頭痛に悩む人は非常に多く、特に仕事やストレスの多い現代社会では慢性的な頭痛に苦しむ人が少なくありません。実際、日本では片頭痛が人口の約5〜10%、緊張型頭痛が約20%に上るとの報告もあり、国民の4人に1人が何らかの頭痛を抱えているとされています。こうした頭痛を和らげるには、市販の鎮痛薬に頼るだけでなく根本原因にアプローチすることが重要です。頭痛の治し方として、日常的なセルフケアの実践や生活習慣の見直しを取り入れることで、痛みの頻度や強さを改善できる可能性があります。
本記事では、中目黒整体anelmaの理学療法士が頭痛を改善するセルフケアのポイントと、整体による専門ケアや生活習慣改善の重要性について解説します。特に多くみられる「緊張型頭痛」と「片頭痛(偏頭痛)」、「群発頭痛」に焦点を当て、それぞれの原因や対策を詳しく見ていきましょう。日々のセルフケアに役立つ情報に加え、当院Instagramのリール動画へのリンクもご紹介しますので、動画も参考にしながら実践してみてください。
頭痛の原因とは?まずは原因を理解しよう
ひと口に頭痛といっても様々なタイプがありますが、ここでは代表的な緊張型頭痛と片頭痛、群発頭痛について、その原因を見ていきます。原因を正しく理解することで、効果的な対処法を選びやすくなります。
1. 筋肉の緊張と血行不良(緊張型頭痛)
長時間のデスクワークやスマートフォン操作などによる前かがみの姿勢が続くと、首や肩まわりの筋肉が凝り固まり血流が悪くなります。このような筋肉の緊張や血行不良は、緊張型頭痛の大きな原因と考えられています。実際、緊張型頭痛は頭から首・肩にかけての筋肉のコリや精神的ストレスによって起こる最も一般的な一次性頭痛です。症状としては頭全体を締め付けられるような重い痛みが特徴で、吐き気や嘔吐は稀なことが多く、痛みを抱えながらも日常生活はなんとか送れる程度のことが多いとされます。
猫背やストレートネックなどの姿勢異常や首・肩のコリが蓄積すると緊張型頭痛を誘発しやすく、夕方になると頭が重く締め付けられるように痛む「首こり頭痛」を感じる場合もあります。また同じ姿勢を長時間続けること自体が首や肩の筋肉に負担をかけ、筋緊張性の頭痛を慢性化させる要因になります。まずは日常の姿勢や動作を見直し、首・肩の筋肉に負担をかけないことが予防の第一歩です。
2. 眼精疲労やストレスによる頭痛
長時間のパソコン作業やスマホの使用で目を酷使すると眼精疲労が生じ、これが頭痛の原因になることがあります。画面を凝視し続けることで目の周りの筋肉が疲労し、首や頭の筋肉まで緊張状態になるためです。同時に、強い光や騒音などの感覚刺激も頭痛を誘発しやすく、オフィスの照明や日常の騒音に敏感な人は注意が必要です。
また、精神的ストレスや緊張の蓄積も頭痛(特に緊張型頭痛)の大きな誘因です。ストレスを感じる場面では交感神経が優位になり、筋肉がこわばって血行が悪くなります。その結果、肩こりや首こりが悪化し、頭痛を招くことがあります。不安や抑うつ状態が続く場合も頭痛発生リスクが高まることが知られています。さらに睡眠不足や逆に寝過ぎといった生活リズムの乱れも頭痛を起こしやすい要因です。自律神経のバランスが崩れると体の回復力が低下し、慢性的な痛みにつながりかねません。
このように、目の酷使やストレス・疲労の蓄積、生活習慣の乱れは頭痛の頻度や程度を悪化させる要因となります。普段から意識して目を休めたり、ストレス発散の時間を作ったりすることが大切です。
3. 片頭痛(偏頭痛)を引き起こす要因
ズキンズキンと脈打つような痛みで知られる片頭痛は、緊張型頭痛とは発生メカニズムが異なる頭痛です。片頭痛は何らかの誘因(トリガー)によって三叉神経が刺激され、痛み物質が放出されることで脳の血管が炎症・拡張し起こると考えられています。代表的な誘因として、体質的な要素やホルモンバランスの変化(月経周期など)、強いストレスからの解放時、睡眠不足や寝過ぎ、アルコール(特に赤ワイン)や特定の食品(チーズやチョコレート)、天候や気圧の変化、強い光や音・匂いなど様々なものが挙げられます。どの誘因で片頭痛が起こるかは人によって異なり、複数の誘因が重なることで発作につながるケースもあります。
片頭痛は動いたり体を働かせたりすると悪化するのが特徴で、光や音に敏感になり日常生活に支障を来すほどの強い痛みになることが多いです。一方で緊張型頭痛は動いても悪化せず、むしろ軽い運動をすることで症状が和らぐ場合もあります。この違いは、片頭痛が血管の拡張によって起こるのに対し、緊張型頭痛は筋肉や血管の収縮によって起こるためであり、痛み発生の仕組みが正反対だからです。したがって、自分の頭痛タイプに合った対処をしないと症状を悪化させてしまうこともあります。
片頭痛の誘因には自分ではコントロールしにくいもの(天候や気圧の変化など)もありますが、生活習慣や環境要因については可能な範囲で避ける工夫が大切です。また、片頭痛のある方でも首や肩のこりを伴うことがあり、緊張型との混在も珍しくありません。
4. 群発頭痛を引き起こす要因
群発頭痛は、片頭痛や緊張型頭痛に比べて発症頻度は低いものの、一次性頭痛の中で症状が最も激しいタイプです。片側の目の奥からこめかみにかけて極めて強い痛みが起こり、その名の通り数週~数ヶ月の期間に群発(集中)してほぼ毎日発作が起こります。発作は主に夜間や明け方に起こり、痛みが続いている間はあまりの激痛にじっとしていられないほどです。頭痛と同じ側で目が充血して涙が出たり、鼻づまりや鼻水、まぶたの垂れ下がり(眼瞼下垂)といった自律神経症状を伴うことも多く、これらも群発頭痛の典型的な症状です。原因は明確には解明されていませんが、脳の視床下部(体内時計を司る部位)の機能異常が関与しているとの説があり、群発期にはアルコール摂取が高い確率で頭痛発作の誘因となることが知られています。
頭痛を和らげるセルフケア|整体師がおすすめする簡単セルフマッサージ&ストレッチ

慢性的な頭痛を改善するためには、日々のセルフケアが欠かせません。ここでは、頭痛持ちの方が日常で実践しやすいセルフケア方法をご紹介します。文章だけでは分かりにくい部分もあるかもしれませんが、当院のInstagramリール動画でも頭痛解消に役立つセルフケアを公開していますので、ぜひ動画も参考にしてみてください
首・肩の筋肉をほぐすセルフケア
緊張型頭痛の多くは首や肩のコリに起因するため、首の筋や肩周辺の筋肉を軽く動かしたりマッサージしたりすることで症状緩和が期待できます。肩をすくめて上下に動かす、首をゆっくり回す・傾けるといった簡単な体操は、デスクワーク中でも取り入れやすいセルフケアです。首や肩に強いこりを感じる場合は、入浴後など筋肉が温まったタイミングでストレッチするとより効果的です。
こめかみ周辺のセルフケア
側頭部の筋肉(側頭筋)が緊張すると頭痛を誘発しやすいため、こめかみ付近を指の腹で優しく円を描くようにマッサージしてみましょう。緊張型頭痛の場合、こめかみを軽くほぐすことで痛みが和らぐことがあります。ただし、強く押しすぎると逆効果になることもあるため、心地よいと感じる強さで行ってください。こめかみ付近はツボ(頷厭(がんえん)など)も集中しているため、適度な刺激は筋肉の緊張を和らげ頭痛を緩和するのに有効です。
温熱・冷却によるケア
頭痛のタイプに応じて、温めるか冷やすかのケアを使い分けることもポイントです。緊張型頭痛で筋肉がこわばっている場合は、蒸しタオルや入浴で首・肩を温め血行を良くすると症状が改善しやすくなります。逆に拍動する痛みが強い片頭痛発作時は、額やこめかみを冷やし、刺激の少ない静かな暗い部屋で安静に過ごすことが勧められます。自宅に冷却ジェルや氷嚢があればタオルにくるんで当て、できるだけ体を休めましょう。吐き気がある場合は無理に何かをせず、静かに横になることが大切です。
リラックス法を活用したセルフケア
ストレス緩和を目的としたセルフケアも頭痛対策に有効です。深呼吸や瞑想、軽いヨガ、アロマテラピーなど、自律神経のバランスを整えるリラックス法を日常に取り入れてみてください。緊張型頭痛はストレスで悪化しやすく、片頭痛も「ホッと一息ついたとき」に起こりやすい傾向があります。そのため、日頃からストレスをため込まないよう意識し、趣味の時間を確保するなど心身をリセットする習慣が頭痛予防・改善につながります。
当院Instagramでもセルフケア方法を発信中!
これらのセルフケアはあくまで応急的・補助的な対策ですが、継続することで頭痛の頻度を減らしたり痛みを感じにくい身体づくりに役立ちます。特に首や肩のこりが慢性的にある方は、毎日の軽いストレッチやマッサージを習慣化してみましょう。セルフケアの詳細なやり方は当院Instagramのリール動画でも紹介していますので、無理のない範囲で実践してみてください。
こめかみ、側頭筋のほぐし方

【セルフケアのやり方】
- こめかみ部分に指をあてる。
- そのまま円を描くように動かす。
- 押す強さは3kgくらい!(わからない方は、少し強めに押してみましょう)
- 20秒続けて、終わったら逆回りで20秒続けます。グリグリグリグリ。
- 今度は側頭筋(耳の上の部分)。指または拳でグリグリしましょう。
- 20秒続けて、終わったら逆回りで20秒続けます。グリグリグリグリ。
- 側頭筋は範囲が広いので、前の方・真ん中・後ろの方と順番に。
- これが終わると視界が良好に。頭痛に効くのでやってみてください!
※ 動画で実践
慢性的な頭痛にお悩みの方は、中目黒整体anelmaでの専門施術をぜひ一度ご相談ください。当院では、豊富な臨床経験を持つ理学療法士が丁寧なカウンセリングと検査を行い、お客様それぞれの症状に合わせた最適な施術をご提供しています。筋肉のこりを緩め血流を改善するアプローチや、骨格・姿勢の調整によって痛みの根本原因に働きかけるオーダーメイド施術を心がけております。「頭痛を根本から改善したい!」とお考えの方は、ぜひ中目黒整体anelmaへご来院ください。つらい頭痛から解放され、健やかな日常を取り戻すためのお手伝いを全力でさせていただきます。
まとめ
この記事では、頭痛(主に緊張型頭痛・片頭痛・群発頭痛)の原因と改善方法について、セルフケアと生活習慣の観点から詳しく解説しました。緊張型頭痛の原因には日常の姿勢悪化や筋肉の緊張・血行不良、精神的ストレスなどがあり、片頭痛の誘因にはホルモン周期や睡眠不足、光・音・天候の変化など多岐にわたることを確認しました。群発頭痛の原因は明確には解明されていませんが、脳の視床下部(体内時計を司る部位)の機能異常が関与しているとの説があり、群発期にはアルコール摂取が高い確率で頭痛発作の誘因となることが知られています。それぞれのメカニズムの違いを理解し、自分の頭痛タイプに合った対処をすることが重要です。
頭痛を和らげるセルフケアの具体的な方法としては、首・肩のストレッチやこめかみ周辺のマッサージ、温罨法・冷却法の使い分け、リラックス法の活用などを紹介し、当院のInstagramリール動画も参考にしながら実践できるようご案内しました。また、頭痛を防ぐための生活習慣の改善ポイント(姿勢の工夫、十分な水分・睡眠、適度な運動、誘因の回避など)についても説明しました。まずはできる範囲でセルフケアと生活習慣の見直しを行い、それでも慢性的な頭痛にお困りの場合は専門の整体施術による根本改善もご検討ください。セルフケアでは対処しきれない頑固な症状も、専門家の施術で改善が期待できる場合があります。
頭痛は適切な対策とケアを継続することで必ず改善の余地があります。「もう頭痛薬に頼る生活は終わりにしたい」「根本から頭痛を治したい」とお考えの方は、ぜひ一度中目黒整体anelmaにご相談ください。私たちと一緒に、つらい頭痛のない快適な毎日を目指していきましょう。