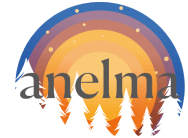目次
はじめに
首こりに悩む人は非常に多く、特にデスクワークが増えた現代では、慢性的な首こりに苦しむ人が後を絶ちません。首こりを和らげるには、日常的なセルフケアを取り入れることが重要です。本記事では、中目黒整体anelmaが推奨する「簡単にできる首こりセルフケア」を詳しくご紹介します。
また、当院のInstagramでも人気のリール動画とともに、実践しやすいセルフケアの方法を解説しますので、動画とあわせて実践してみてください。
首こりの原因とは?まずは根本を理解しよう
首こりを効果的に改善するためには、まずその原因を理解することが重要です。原因を知らずにマッサージやストレッチをしても、一時的な効果しか得られない場合が多いためです。
1. 姿勢の悪化(ストレートネック・スマホ首)
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、頭が前に突き出た姿勢(ストレートネック・いわゆる「スマホ首」)が続くと、首こりが悪化しやすくなります。頭が前方にある前傾姿勢では、首や肩周辺の筋肉に大きな負担がかかり、血流が悪くなる原因となります。その結果、筋肉に十分な酸素や栄養が行き渡らず、首のこりや痛みにつながります。
2. 筋肉の緊張と血行不良
ストレスや運動不足により筋肉が緊張すると、血流が滞り、疲労物質が蓄積されて首こりを引き起こします。特に長時間同じ姿勢でいると、首周りの筋肉が固まりやすくなり、慢性的なコリにつながります。デスクワーク中に肩や首を動かさずにいると、知らないうちに筋肉に疲労が溜まり、血行不良が進行してしまうのです。
3. 眼精疲労やストレス
目の疲れや精神的なストレスも、首こりの原因になります。パソコンやスマートフォンを長時間使用すると、目の周りの筋肉が疲労し、その緊張が首や肩の筋肉にも波及します。さらに、仕事上のプレッシャーなど精神的ストレスは無意識に首や肩の筋肉をこわばらせ、こりを悪化させる要因となります。
首こりの原因は他にも様々あります。詳しく知りたい方は、当院の別記事『首こりの原因』もぜひご覧ください。
関連記事 > 首こりの原因とは?多くの働く世代を悩ませる症状の背景にあるもの
首こりを解消するセルフケア|整体師おすすめのストレッチ&マッサージ
首こりを改善するためには、日々のセルフケアが欠かせません。ここでは、当院のInstagramで人気の「首こり解消セルフケア」リール動画をもとに、具体的なストレッチ方法をご紹介します。文章だけではわかりにくい部分もあるかと思いますので、ぜひリール動画を視聴しながらセルフケアをしてみてください。
首を直接ほぐすセルフケアのご紹介
単純に手を使って【首を直接ほぐす】セルフケアのご紹介です。
【セルフケアのやり方】
- 手を首(頭の後ろで髪の生え際あたり)にしっかり押し当てて、グリグリモミモミほぐしていきます。コツとしては、皮膚を滑らすのではなく、しっかり筋肉に押し当てて、そこからグリグリモミモミしていきます。
- 上下に満遍なく、グリグリモミモミ、しっかりほぐしていきます。
- 片側が終わったら、今度は反対側もやります。しっかり押し当てて、上限に満遍なくです。
- これが終わると、首がスッキリしていますよ。
※ 動画で実践![首こりのセルフケア動画(当院のInstagramへ!)]
後頭下筋の緩め方
後頭下筋(こうとうかきん)は頭の付け根(後頭部と首の境目)にある小さな筋肉群で、長時間のデスクワークや眼精疲労により緊張しやすい部位です。後頭下筋が硬くなると、頭が重く感じたり、頭痛の原因になったりします。この部分をほぐしてあげることで、首の付け根のこわばりが取れ、頭の重さや首こりの軽減につながります。
【セルフケアのやり方】
- 両手の親指を使って、頭の後ろで髪の生え際あたり(後頭骨のすぐ下)にあるくぼみ部分に軽く当てます。そこが後頭下筋のある場所です。
- そのままの位置で、グリグリモミモミほぐします(20秒〜30秒)。
- もしくは同じところ(後頭骨)に指を引っ掛ける形で、じわ〜っとぐわ〜っと押し当てる(20秒〜30秒)という方法もあります。
- コツとしては、手を置いたまま“首を少し後ろに傾ける”ことです。その状態で待つか、揉みほぐすかしていきましょう。
- 終わったら、反対についても同じようにほぐしていきましょう。グリグリモミモミほぐすか、じわ〜っとほぐしていきましょう。
※ 動画で実践![後頭下筋のセルフケア動画(当院のInstagramへ!)
ボールを使った後頭下筋のほぐし方
後頭下筋はデスクワークでパソコンの画面をずっと見ている方やスマホをずっと見ている方は特に硬くなりやすいです⚠️
硬くなると⚠️首肩こり⚠️頭痛⚠️めまいなど、たくさんの症状が出やすくなってしまうので、要注意です
【セルフケアのやり方】
- 後頭骨に指をあてて、そのまま下にスライドさせます。ぽこっと凹んでいるところがありますので、そこをほぐしていきます。
- 今回はボールを使ってほぐしてみましょう。凹んでいるところにボールを押し当ててみましょう(押し方のコツは、ボールが頭を貫通するイメージで、グイーッと押します。
- 頭をボールの上に乗せて、20〜30秒間キープします。これが終わったら、ボールを横にズラします。少し後にズラして、また頭をボールの上に乗せていきます。
- コツとしては、ボールが後頭骨のヘリに当たるように押し当ててあげると、よりほぐれますよ。これを後頭骨の端から端までしっかりほぐしていくと、首の回しやすさ・見上げやすさが爆上がり!
※ 動画で実践![ボールを使った後頭下筋のセルフケア動画(当院のInstagramへ!)]
首こりを防ぐ生活習慣
セルフケアだけではなく、日常生活全体の見直しも首こり解消には欠かせません。ここでは、首こりを防ぐための日々の生活習慣の改善ポイントについて詳しく説明します。
規則正しい生活リズムを心がけることで、筋肉の緊張や疲労の蓄積を防ぎ、首こりの発生リスクを大幅に低減させることができます。具体的には、以下の点が推奨されます。
定期的なストレッチと適度な休憩
長時間のデスクワークやスマホ操作の合間に、定期的に肩や首を動かしましょう。1時間に一度は立ち上がってストレッチを行うことで、筋肉の緊張をほぐし、血行不良を防ぐ効果があります。
バランスの取れた食事と十分な睡眠
栄養バランスの良い食事を心がけ、睡眠時間をしっかり確保しましょう。体が十分に回復することで筋肉のこわばりが軽減し、血流の改善にもつながります。
適度な運動の取り入れ
日常に軽い有酸素運動やウォーキングの習慣を取り入れると、全身の血液循環が促進され、首こりの予防に効果的です。運動によってストレス発散にもなるため、一石二鳥と言えます。
これらの生活習慣を実践することでセルフケアの効果をより高め、慢性的な首こりの改善や予防が期待できます。
首こりが改善しないなら整体での施術も検討を
自己流のセルフケアだけで十分な改善が見られない場合、プロフェッショナルによる施術を検討することも重要です。専門の整体施術では、筋肉の緊張を根本からほぐし、血流の改善を促すことで首こりの原因に直接アプローチします。
当院「中目黒整体anelma」では、患者様一人ひとりの状態をしっかりと診断し、オーダーメイドの施術プランを提案しています。セルフケアでは得られなかった効果や、慢性的な首こりの根本改善に向けて、専門家の視点からサポートいたします。
専門スタッフによる丁寧なカウンセリング
経験豊富なスタッフが首こりの症状や生活習慣を詳しくお伺いし、お客様に最適な施術方法を考案します。
筋肉の深部まで届く施術と血流促進
凝り固まった筋肉を的確にとらえ、深部からほぐす施術を行います。あわせて血行を促進し、痛みやこりの根本原因にアプローチします。
専門の施術とセルフケアを組み合わせることで、首こりの悩みを効果的に解消することが可能です。「なかなか首こりが改善しない」「根本から良くしたい」という方は、一度当院にご相談いただくことをおすすめします。
中目黒で首こりを根本から改善するなら「中目黒整体anelma」へ
首こりでお悩みの方へ|関連記事もチェック
首こりについてさらに詳しく知りたい方や、他の症状との関連性についても学びたい方は、当院の過去の記事もぜひご覧ください。多角的な視点から首こりを捉えることで、自分に最適な対策を見つけるヒントになります。
関連記事では、首こり以外の身体の不調や具体的な施術例、患者様の声なども紹介しており、全身の健康改善を目指すための情報が満載です。
- ブログ > 首こりの原因とは?多くの働く世代を悩ませる症状の背景にあるもの(首こりの主な原因について詳しく解説した記事)
まとめ
この記事では、首こりの原因とその解消法を、Instagramのリール動画を活用しながら詳しく解説しました。
首こりの原因には、日常生活での姿勢の悪化や筋肉の緊張、血行不良など様々な要因が絡み合っています。
また、生活習慣の見直し(定期的なストレッチや十分な休息、適度な運動)も首こり予防に効果的です。
それでも首こりが改善しない場合は、専門の整体による根本施術も検討してください。
「首こりを根本から解消したい!」とお考えの方は、ぜひ一度「中目黒整体anelma」へご来院ください。皆様の健康をサポートすべく、丁寧かつオーダーメイドの施術を提供しております。